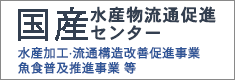おうちでFish-1グランプリ-ONLINE-に出品
している県の水産業やプライドフィッシュ、地魚などについてクイズで出題!
産地
1.青森県(
Q1.青森県
答
A1.日本海側
クロマグロは南
Q2.大間
答
A2.定置網漁業
対馬海流
Q3.マグロ以外
答
A3.ホタテガイ
約
青森県
2.山形県(
Q1.山形県
答
A1.庄内
山形県
Q2.山形県
答
A2.サケ(アキサケ)
主
Q3.山形県
答
A3.庄内浜文化伝道師
庄内浜
3.富山県(
Q1.三方
答
A1.シロエビ
主
Q2.ホタルイカの名前
答
A2.発光
発光器
Q3.ブリは出世魚
答
A3.福来魚
大漁
富山県
4.福井県(
Q1.福井県
答
A1.リアス海岸
複雑
Q2.ふくいサーモンなどのサケ類
答
A2.アスタキサンチン
強
Q3.ふくいサーモンは最初
答
A3.約
人工種苗
5.千葉県(
Q1.千葉県
答
A1.10年
主
Q2.千葉県
答
A2.たて縄釣
メインとなる糸
Q3.千葉県
答
A3.勝浦沖
「銚子
千葉県
6.兵庫県(
Q1.三方
答
A1.北
北部
Q2.兵庫県
答
A2.カタクチイワシ
シラスは主
Q3.漁獲
答
A3.きれいもん
生
兵庫県
7.岡山県(
Q1.岡山県
答
A1.紀伊水道
特
Q2.プライドフィッシュ「ほんに良
答
A2.一番草
新芽
Q3.プライドフィッシュ「岡山
答
A3.アナゴ筒漁
アナゴはストレスで弱
岡山県
8.香川県(
Q1.瀬戸内海
答
A1.産卵場
流
Q2.香川県
答
A2.2011年
東日本大震災
Q3.「讃岐
答
A3.4種類
ナツメグ、オレガノ、シナモン、ジンジャーのハーブをブレンドした専用
香川県
9.愛媛県(
Q1.愛媛県
答
A1.マダイ
愛媛県
Q2.「本当
答
A2.愛育
ビタミン群
Q3.「鯛
答
A3.熱々
10.大分県(
Q1.大分県
答
A1.臼杵市
それぞれが湾
Q2.大分県
答
A2.かぼすヒラメ
餌
Q3.大分県
答
A3.あつめし
甘辛
大分県
11.鹿児島県(
Q1.養殖
答
A1.鹿児島県
ウナギは主
Q2.養殖
答
A2.体内
出荷前
Q3.魚
答
A3.トビウオ
大
鹿児島県